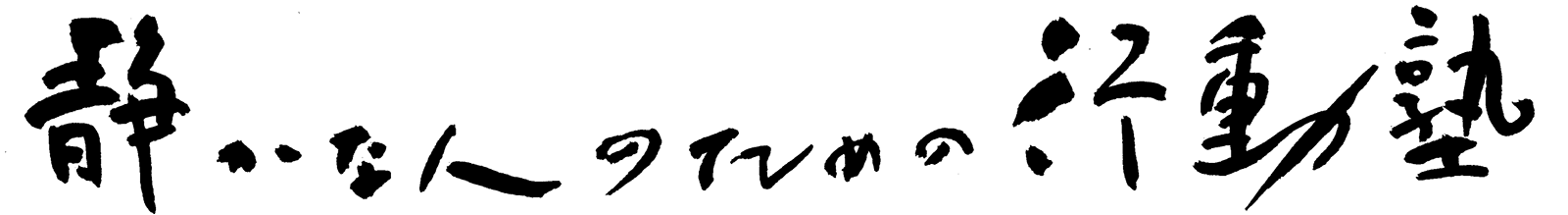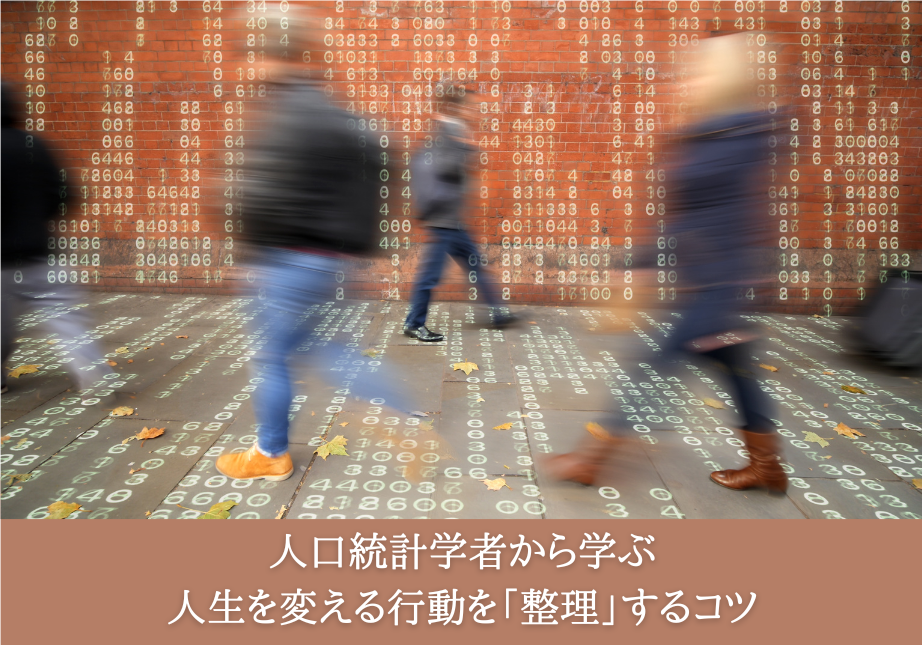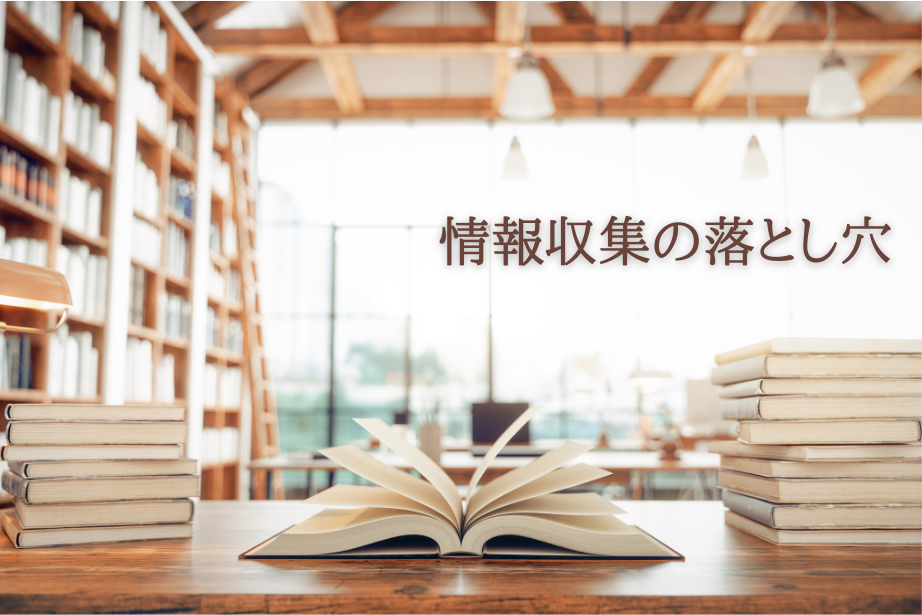こんにちは、佐々木翠です。
今、人口統計学者エマニュエル・トッドさんの『我々はどこから来て、今どこにいるのか?』という本を読んでいます。
本そのものは、世界の人類史を「家族」という切り口で考察したものなのですが、
人生と行動にも通じる話があったのでシェアします。
ちょっと理屈っぽいので、今そんな気分じゃないよ〜という方はスルーしてくださいね。
人間社会を眺めるときの3層モデル

世界各地の人間社会を見るとき、
どんな社会で・これからどうなるのか? は
その社会を「3つの層モデル」で考えることができるそうです。
3つの層って・・・?
まず一番表面にあって分かりやすい層が「政治・経済」だとか。
ミルフィーユで言うところの一番上の粉砂糖がかかっているところ、という感じでしょうか。
そして、その下にある層が「教育」で
一番下の意識されにくい層が「家庭・宗教」
とのこと。
※トッドさんは、フロイト精神分析(心は意識・下意識・無意識から構成されているという説)からこのモデルの着想を得たそうですよ。
面白いなと思いました。
なぜなら、この3つの層に時間軸(どのくらいのスパンで変化するか)を追加してみると、ミルフィーユの上側から下側へ向かって・・・
- 第1層:外から見えやすく、具体的で、変えやすいこと(短期)
- 第2層:変えられるけど、分析や計画が必要で、時間のかかること(中長期)
- 第3層:外から見えにくく、抽象的で、ほとんど変わらないこと(長期)
と見事に分かれるからです。

本では人間社会の話ですが、
実はこれって、自分がどんな人間で・これからどう変化するのか を考える時にも役に立つと思いませんか?
3層モデルで整理できる 私たちの人生と行動
人生を変えるために何をすれば?と漠然と考えるだけだと
”考えることが多すぎて、結局なんにもしない” となってしまいますが
3層モデルを意識すると、もう少しスッキリします。
そうですね、たとえば・・・
第1層(短期)|日常の延長線でできる行動。日々の生活で家庭や仕事を大事にする、成長につながる習慣を続ける、ポジティブなメッセージに触れる、良い人間関係をつくる、など。
第2層(中期)|5〜10年スパンでできる行動。過去を棚おろしして自分を肯定する、望む未来を考えてプランを練る、今後のために新しいことを始める、など。
第3層(長期)|ちょっとやそっとじゃ変化しない自分の芯。好きなことや苦手なこと、価値観、セルフイメージ、など。
ざっくりですが、なんとなく伝わるでしょうか?
- 明日からできる行動
- 時間がかかるけれど大事な行動
- 無理に変える必要はないもの
の3つに整理するイメージです。
ひとくちに「人生と行動」といっても、深さの違う層があるのですね。
すぐできることと時間のかかること:組み合わると相乗効果あり

社会で教育の効果が出るのに10年スパンの時間がかかるように、自分がどんな人間で・これからどうなりたいのか、を発掘するのにも時間がかかるのが普通です。焦らなくて大丈夫です。
そして、時間をかけて考えたことや一見無駄に見える行動は、絶対にあなたを裏切りません。
「行動したけどあれは無駄だった」と感じるのは、ものを測る時間スパンが短すぎるだけの場合がほとんどです。
このことはぜひ覚えておいてくださいね。
さて、今日は人生と行動を考えるときの3つの層と時間軸がテーマでした。
3つの層は独立しているわけではなく、お互いにリンクしながら変化していきます。
すぐにできることを積み重ねながら、中長期的にどうなりたいのかも考えていく。そして少し行動して変化を感じると、それに連動してセルフイメージも少しずつ変わっていく。
そうやって時間軸の違う3つの層をうまく組み合わせながら成長していく、ぜひそのことを意識してみてください。
では今日はこのあたりで。
最後まで読んでくださってありがとうございました。
佐々木翠